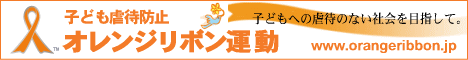“くろまうす”こと粕谷幸司は、KASUYA.net - かすやどっとねっとに移転しました。
がっつり素人目線のPRマン“くろまうす”がお送りする、忍者のサービスについてだったり、小ネタだったり日常に転がるニュースだったり…よろずテーマの忍者ブログ。
Apr 09,2010
“戦士”は死語じゃなく思想にすべきだ
社会人3年目の僕は考えていた。
(完全に勝手な見解なので、取り扱いには注意して欲しい)
最近、企業戦士だとかIT戦士だとかいう言葉を聞かない気がする。
「企業戦士」という言葉は、Wikipediaによると以下のように紹介されている。
けれど、時代の変化からか、最近ではこういう“命をかけて”とかの暑苦しい考え方は古の存在になりつつあるように感じる。
命をかけても、リストラされる。
個人の幸福は、戦場の外に存在する。
汗水たらして働くより、効率良く頭を使う。
そんな考え方が重要視されてきた気がする。
けれど、戦士たちの中身は実は何も変わっていなくて。
ただ戦争が以前より緻密な戦略によって繰り広げられるべきものへと変化し、目に見えることの無い戦いばかりが点々となされているから、表面上の平和というものが成り立っているような錯覚に陥って、戦士たちはその熱意の行き場を見失っているんじゃないだろうか。
全世界の平和を目指すのなら、潰し合う・出し抜き合う今の商売の仕方は間違っているはずだと、本当の平和主義は思ってもおかしくない。
けれど企業には大抵の場合“競合他社”という存在があって、相手を食うように自軍が勢力を増していかない限り生き残ってはいけない。
だから、今もまだ戦士たちは、戦い続けている。
IT業界においても、続々と競合他社が生まれては、パクりパクられながらも切磋琢磨を繰り返している。
ひと昔前までの起業ブームでは顕著にその“死闘ぶり”が表面化していたけれど、今やそれも慣習化してモヤモヤと“巨大勢力がいくつかある周りに弱小軍が悶々としながら生き延びている”ような状況になりつつあるように思えてならない。
そんな時代にこそ、“戦士”へのメッセージが必要なんじゃないか?
戦士だった人々、戦士に憧れ大きな夢を持っていた人々の、稚拙で馬鹿げていて暑苦しいだけの“熱意”だとしても、それを呼び覚ますことに意味があるように思える。
「戦争を起こせ」だなんて正気の沙汰ではないようなことは絶対に言わないけれど。
戦士たちは、戦い続ける種族として、もっと熱くなっても良いと思う。
ベジータやフリーザ、セルや魔人ブウと戦い続けたZ戦士たちは、いつも熱く強く生き続けていたが、勉強はあまりしていなかった。
勉強も大事だけれど、もっと大事なのは熱意だ。
知識や戦略も重要だけれど、戦士たちの熱意こそを僕は全力で支持する。
(完全に勝手な見解なので、取り扱いには注意して欲しい)
最近、企業戦士だとかIT戦士だとかいう言葉を聞かない気がする。
「企業戦士」という言葉は、Wikipediaによると以下のように紹介されている。
企業戦士 (きぎょうせんし) は日本において企業のために粉骨砕身で働く勤め人であるサラリーマンをいう。自らの身も家庭や家族をも顧みず会社や上司の命令のままに働く姿を戦場での兵士に例えたものだが、日本の屋台骨を支える「戦士」であると企業や社会からもてはやされ、高度経済成長以降「日本株式会社」のおもな担い手となった。まさに社会を戦場に例え、そこで命をかけて戦い続ける人々を“戦士”と称していた。
けれど、時代の変化からか、最近ではこういう“命をかけて”とかの暑苦しい考え方は古の存在になりつつあるように感じる。
命をかけても、リストラされる。
個人の幸福は、戦場の外に存在する。
汗水たらして働くより、効率良く頭を使う。
そんな考え方が重要視されてきた気がする。
けれど、戦士たちの中身は実は何も変わっていなくて。
ただ戦争が以前より緻密な戦略によって繰り広げられるべきものへと変化し、目に見えることの無い戦いばかりが点々となされているから、表面上の平和というものが成り立っているような錯覚に陥って、戦士たちはその熱意の行き場を見失っているんじゃないだろうか。
全世界の平和を目指すのなら、潰し合う・出し抜き合う今の商売の仕方は間違っているはずだと、本当の平和主義は思ってもおかしくない。
けれど企業には大抵の場合“競合他社”という存在があって、相手を食うように自軍が勢力を増していかない限り生き残ってはいけない。
だから、今もまだ戦士たちは、戦い続けている。
IT業界においても、続々と競合他社が生まれては、パクりパクられながらも切磋琢磨を繰り返している。
ひと昔前までの起業ブームでは顕著にその“死闘ぶり”が表面化していたけれど、今やそれも慣習化してモヤモヤと“巨大勢力がいくつかある周りに弱小軍が悶々としながら生き延びている”ような状況になりつつあるように思えてならない。
そんな時代にこそ、“戦士”へのメッセージが必要なんじゃないか?
戦士だった人々、戦士に憧れ大きな夢を持っていた人々の、稚拙で馬鹿げていて暑苦しいだけの“熱意”だとしても、それを呼び覚ますことに意味があるように思える。
「戦争を起こせ」だなんて正気の沙汰ではないようなことは絶対に言わないけれど。
戦士たちは、戦い続ける種族として、もっと熱くなっても良いと思う。
ベジータやフリーザ、セルや魔人ブウと戦い続けたZ戦士たちは、いつも熱く強く生き続けていたが、勉強はあまりしていなかった。
勉強も大事だけれど、もっと大事なのは熱意だ。
知識や戦略も重要だけれど、戦士たちの熱意こそを僕は全力で支持する。
…なんてことをぼんやりと考えていたんですよ。
まだまだ若造の癖に、ナマ言って本当にスミマセン。
これからも頑張りまうす。
PR
- ちょっと普通に
- COMMENT(0)
- 2010.04.09 12:04
Form
Latest entries
(05/16)
(02/03)
(10/21)
(10/14)
(09/03)
(08/16)
(07/30)
(07/21)
(07/20)
(07/16)
(07/15)
(07/10)
(07/08)
(07/04)
(07/04)
(06/27)
(06/18)
(06/17)
(06/14)
(06/10)
Archive
ブログ内検索
[PR]